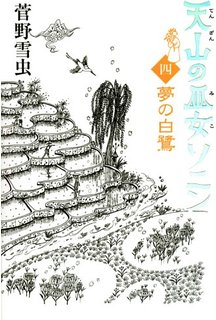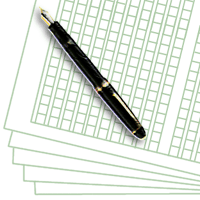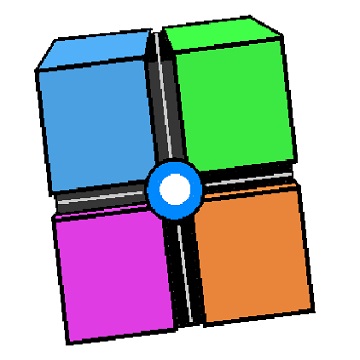ドイツやオーストリアあたりを旅すると彼の地の歴史の中に必ず登場するのがハプスブルグ家。神聖ローマ帝国皇帝を代々輩出し、ローマ帝国解体後は後継国家であるオーストリア帝国皇帝の座を守り続けた、欧州第一の名家である。
標題の書は、「オーストリア帝国最後の皇帝」フランツ・ヨーゼフ一世の妃にして、絶世の美女の誉高いエリザベート(エリーザベトとも)の後半生を描いた一作。著者のインゲハイム氏は、ハプスブルグ家の各人物の伝記を「専門」としている方。日本でいうところの「皇室ジャーナリスト」の先駆者的な存在だ。エリザベート皇妃の著作だけで12冊上梓し、累計発行部数は500万部を超えるとのこと。いやはや。小室圭氏のいかがわしさを追求しただけではせいぜい週刊誌のネタにしかならない日本とは違うマーケットが広がっているようである。
さて、本書は、長年に渡り姑として王室に「君臨」したゾフィー大公妃との確執で疲弊したエリザベートが、ゾフィーの逝去により、ようやく王室の第一人者として振る舞えるようになった時代から始まる。王室の権威の維持や子供達の教育方針などにことごとく口を出してくる大公妃という重しが取れたエリザベートは、気ままな長期休暇をとったり、三女のマリー・ヴァレリーを母として慈しんだり、自身の美貌の維持のために極端な食事を摂ったりする。
フランツ・ヨーゼフ帝とはラブラブな関係ではあるが、この当時の常として帝には愛人がいたし、愛が深いゆえに、多忙な帝を気遣って、女優のカタリーナ・シュラットとの仲を取り持ったりもする。最も帝とシュラットとの間柄は「友人関係」以上には発展しなかったようではあるが…。王室全体の「母」として振る舞う姿はある意味痛々しい。周囲には気ままな一人旅を楽しんでばかりいると思われていたが、どっこい、さまざまなプレッシャーから逃れるための逃避行であったことが語られる。
そんな皇妃を二つの悲劇が襲う。一つはバイエルン公ルートヴィヒ二世の不審死。彼はエリザベートにとっては従兄弟の子供というやや遠い親族ではあったが、幼少期から一緒に過ごした時期が長く、親しみを持つ間柄であったし、自分と同じような「カゴの鳥」という境遇にシンパシーを感じる人物だった。
そして皇太子ルドルフの心中事件。オーストリア帝国の皇帝後継者としての重圧に耐えきれなくなっていたルドルフは、皇太子妃シュテファニーとの夫婦仲が冷え切っていたこととも相まって、マリー・ヴェッツェラという17歳の愛人と心中してしまうのだ。エリザベートの悲しみは深く、この事件後は一生を喪服で過ごした。
この事件から9年後、ジュネーブ・レマン湖畔でイタリア人の無政府主義者ルイジ・ルケーニに刺殺されて61歳の生涯を閉じることになる。ルケーニは「働かざる者食うべからず」という自身の信条に反する王族を憎悪しており、警備の薄い一人旅(とは言っても近習の人間は少なからずいたはずだが)を好むエリザベートは格好の標的だった。
いやはや。多かれ少なかれ、人間というのは自分の周囲の環境に影響されるものではあるが、この時代のオーストリア皇帝妃という立場はあまりにも一人の人間が背負うには重すぎたようだ。まさに皇妃という「立場」に翻弄された一生であったと言える。夫との生活も、母としての幸せも、一人の女性としての生涯も、全て自身の意思とは関係ない出来事で左右されてしまう。私なら、とっとと自殺でもなんでもしてこんな立場を捨ててしまうだろうと感じた。
同時にエリザベートほどの激動はないにせよ、自分の立場から逃れることのできない雅子皇妃の境遇を改めてお気の毒に感じた。さぞかし毎日、息が詰まるような生活を強いられてるんだろうな。そりゃ病気にもなるわ。平民の窓際ダメリーマンやってる方がよほど気楽でいいや。いささか話の本筋から外れた感慨とともに本を閉じたが、こうした彼我の差について改めて考え、今の自分の姿にある種の安心を覚えるというのも王室ジャーナリズムに触れたさいの一つの効用であろう。